EBSD読本
| 商品名 | 「EBSD 読本=OIMを使用するにあたって= (B 4.00)」 |
| 著 者 | 株式会社TSLソリューションズ 代表取締役 鈴木 清一 |
| 価 格 | 10,000円(税込)+送料800円(税込) |
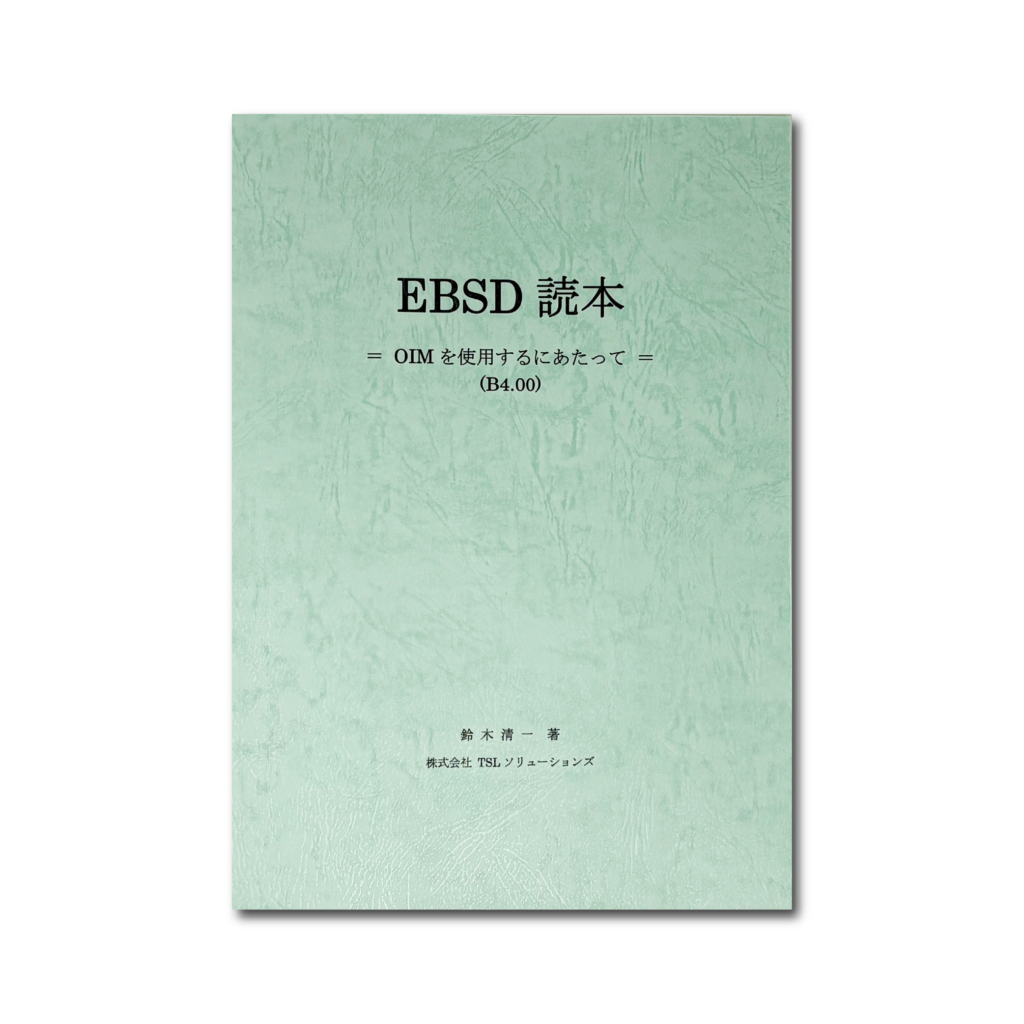
「EBSD 読本 =OIM を使用するにあたって=」は、EBSD 法の教科書的なものとしてEBSD 法の理解の一助となればという思いで、2003年に第1版を発行して以来改定を重ね、現在第4版を発行しております。
掲載一例として、EBSDパターンの発生に関しては、その物理現象に基づき詳細な説明を行っています。データ解析に関しては、結晶方位の表現と極点図・逆極点図の理解に重点を置き、結晶方位に基づく解析、結晶粒と結晶粒界の解析、結晶方位差の解析等を章立てし、データ解析を体系立てて説明しています。また第4版では、EBSDパターンを用いた弾性歪み解析に関し新たに章を追加し説明しています。
詳細につきましては、こちらの目次をご参照ください。
- 前編:OIM/EBSD法で結晶方位マップデータを得るまで
- 0. はじめに
- 0.1 EBSD法の歴史
- 0.2 EBSD法とは
- 1. EBSDパターンの形成
- 1.1 EBSDパターンの概要
- 1.2 EBSDパターンの発生原理
- 1.3 EBSDパターンの発生領域(試料中でのビームの広がりについて)
- 1.4 EBSDパターンの空間分解能
- 1.5 EBSDパターンの発生と試料傾斜角の関係
- 1.6 試料傾斜角と空間分解能の関係
- 1.7 EBSDパターンの明るさ中心
- 1.8 透過EBSD法
- 1.8.1 試料傾斜角とWDの透過EBSDパターンに及ぼす影響
- 1.8.2 試料厚さとEBSDパターンの関係
- 1.8.3 試料厚さと空間分解能の関係
- 1.8.4 試料傾斜角が分解能に及ぼす影響
- 1.8.5 透過EBSD法における試料厚さと加速電圧の関係
- 1.8.6 透過EBSDパターンは試料のどこで形成されるか
- 1.8.7 軸上に配置した検出器で透過EBSDパターンは得られるか
- 1.9 水平に置いた試料からのEBSDパターン
- 2. 結晶方位の表現と結晶構造の分類に関して
- 2.1 単位胞の表現
- 2.2 結晶方位の表現
- 2.3 結晶面の表現
- 2.4 六方晶の3指数表示
- 2.5 結晶系の分類
- 2.6 7つの結晶系具体例
- 2.6.1 三斜格子(Triclinic)[空間群:1~2]
- 2.6.2 単斜格子(Monoclinic)[空間群:3~15]
- 2.6.3 斜方格子(または直方格子Orthorhombic)[空間群:16~74]
- 2.6.4 正方格子(Tetragonal)[空間群:75~142]
- 2.6.5 三方格子(Trigonal)[空間群:143~167]
- 2.6.6 六方格子(Hexagonal)[空間群:168~194]
- 2.6.7 立方格子(Cubic) [空間群:195~230]
- 2.7.1 PZTの場合
- 2.7.2 FCC⇔HCP変態の場合
- 3. EBSDパターンにおけるバンドの検出
- 3.1 EBSD用検出器
- 3.2 CCDチップとCMOSチップの違い
- 3.3 EBSDパターンの画像処理
- 3.4 Hough変換法
- 3.5 キャリブレーション
- 3.6 キャリブレーションの位置補正
- 4. EBSDパターンのバンドの指数付けと結晶方位の決定
- 4.1 材料ファイル
- 4.2 面間角度の測定による指数付けと結晶方位の決定
- 4.3 検出すべきバンド数
- 4.4 EBSD測定の座標系
- 4.5 オイラー角について
- 4.6 結晶方位の計算
- 4.7 指数付けの自動化
- 4.8 信頼性指数(CI値)
- 4.9 フィット指数(Fit値)
- 4.10 ランキング指数
- 4.11 解の平均化
- 4.12 相の分離
- 4.13 相の特定
- 5. SEMについて
- 5.1 EBSD用検出器の取り付け
- 5.2 電子銃の種類と照射電流量およびEBSD用検出器の設定条件
- 5.3 対物レンズの種類
- 5.4 試料の傾斜およびフォーカスの傾斜補正による影響
- 5.5 電子線のスキャンと試料回転
- 5.6 電子線スキャン像と試料座標系の関係
- 5.7 SEMの倍率と分解能の関係
- 5.8 OIMにおけるピクセル形状
- 5.9 測定時のStepSizeと空間分解能
- 5.10 測定領域および測定点数と統計誤差の関係
- 5.11 低真空SEMとEBSD
- 6. EBSD観察用試料の準備に関して
- 6.1 EBSD用試料作製の流れ
- 6.1.1 試料の切り出し
- 6.1.2 包埋等による試料の固定
- 6.1.3 面出し研磨
- 6.1.4 精密研磨/仕上げ琢磨
- 6.1.5 試料研磨によるダメージ層
- 6.1.6 試料表面の変質に関して
- 6.1.7 電解研磨/ケミカルエッチング
- 6.1.8 イオンエッチング
- 6.2 試料表面の平滑度
- 6.3 導電性コーティング
- 6.4 試料の固定方法
- 6.5 具体的な試料作製の例
- 6.6 試料作製全般に関して
- 7. 結晶方位の表現と極点図・逆極点図
- 7.1 結晶方位に着目した結晶方位の表現-極点図-
- 7.2 試料座標に着目した結晶方位の表現-逆極点図-
- 7.3 極点図・逆極点図の強度表現
- 8. 結晶方位に関するデータ解析
- 8.1 データの評価に用いられる非方位関係のマップ
- 8.1.1 イメージクォリティ(IQ)マップ
- 8.1.2 信頼性指数(CI)マップ
- 8.1.3 フィット指数(Fit)マップ
- 8.1.4 IQ/CI/Fitマップの解釈の一例
- 8.2 マップを中心とした結晶方位データの表現
- 8.2.1 逆極点図方位(IPF)マップ
- 8.2.2 一方向結晶方位(CD)マップ
- 8.2.3 特定方位結晶方位(CO)マップ
- 8.3 CDマップと極点図・逆極点図による配向性の評価
- 8.4 結晶方位マップと極点図・逆極点図の関係
- 8.5 ODF(配向分布関数)
- 9. 結晶粒および結晶粒界の定義とその表現
- 9.1 結晶粒の定義
- 9.2 結晶粒界について
- 9.2.1 結晶粒界の定義
- 9.2.2 結晶方位差の計算方法
- 9.2.3 様々な粒界や境界の表現法
- 9.2.4 対応粒界(CSL粒界)と双晶
- 9.3 特定の粒界を排除した結晶粒の認識
- 9.4 平均結晶粒径の計算
- 10. 結晶方位差に基づくマップの表現
- 10.1 結晶粒に基づいた方位差解析
- 10.1.1 平均結晶方位について
- 10.1.2 Grain Orientation Spread (GOS)
- 10.1.3 Grain Average Misorientation (GAM)
- 10.1.4 Grain Reference Orientation Deviation (GROD)
- 10.2 カーネルに基づいた方位差解析
- 10.2.1 Maximum Misorientation AngleがKAMマップに与える影響
- 10.2.2 StepSizeがKAMマップに与える影響
- 10.3 各結晶方位差マップの比較
- 11. EBSDとEDSの同時検出
- 11.1 EBSDとEDS同時検出のための検出器配置
- 11.2 EBSDパターンにおける相分離の実態
- 11.3 EBSDとEDS同時検出のデータ処理
- 11.4 Phase Cluster Analysis
- 11.5 EBSDとEDS同時検出法の課題
- 12. EBSDパターンを用いた弾性歪み測定
- 12.1 EBSDパターンを用いた弾性歪み測定の原理
- 12.2 格子歪みの数学的表現
- 12.3 EBSDパターン上のズレ量の検出
- 12.4 回転成分の検出
- 12.5 弾性歪み分布測定の検証
- 12.6 多結晶体の弾性歪み測定
- 12.7 剛体回転の補正
- 12.8 弾性歪みにおける絶対値測定の可能性
- 12.8.1 歪フリーの参照パターン
- 12.8.2 キャリブレーション点の精度について
- Appendix
- 1.8.6 透過EBSDパターンは試料のどこで形成されるか
